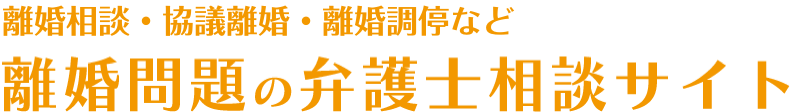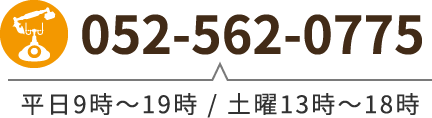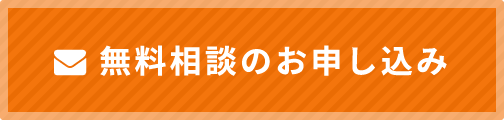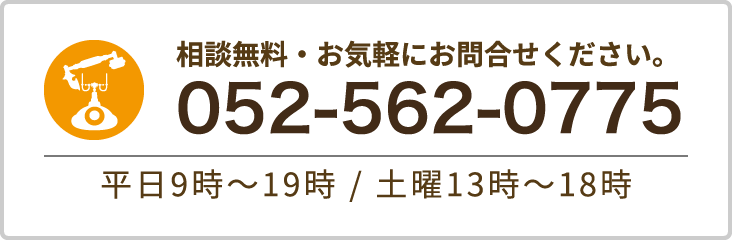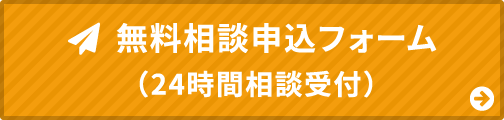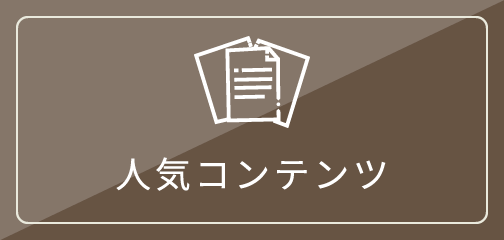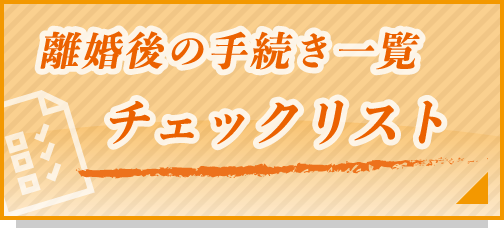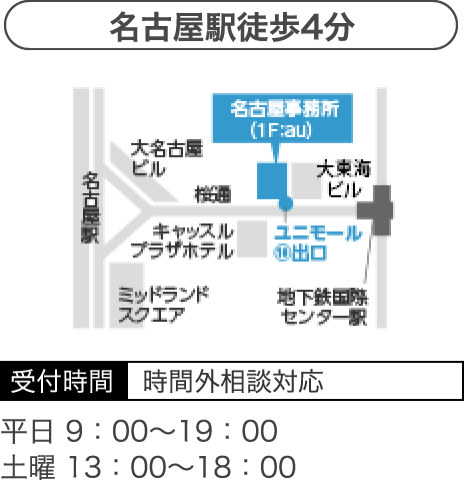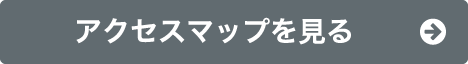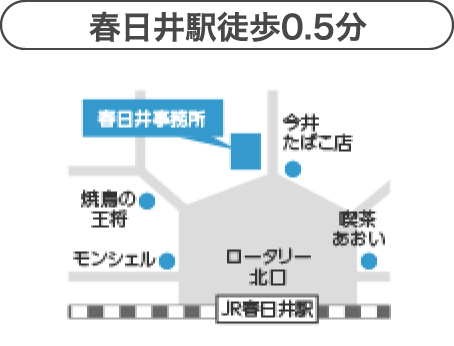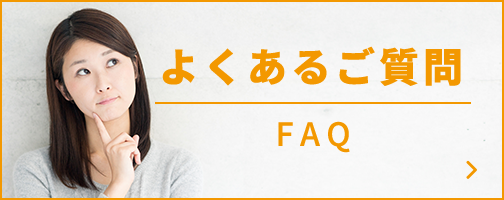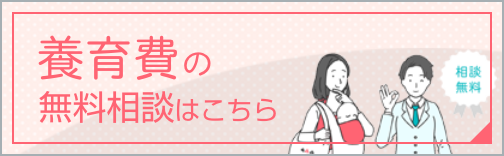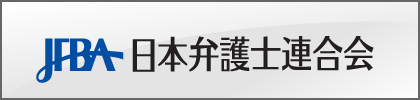年金分割とは、離婚をした場合に、夫婦であった期間に、夫婦が加入していた厚生年金の老齢厚生年金について、保険料の納付実績を、一定の按分割合に基づいて、報酬比例部分の多い方から少ない方へ分割する制度です。
1.年金分割の対象
年金分割の対象となるのは、厚生年金の老齢厚生年金部分です。
日本には、全国民共通の国民年金制度と、企業や官庁などに勤めている人が加入する厚生年金保険制度があります。
国民年金加入者は、年金保険料を納付し、一定の年齢に達すると、老齢基礎年金を受け取ることができます。
さらに、一定の条件を満たした厚生年金加入者は、老齢基礎年金に上乗せして、老齢厚生年金も受け取ることができます。
老齢基礎年金が夫婦それぞれに支給されるのに対して、老齢厚生年金は、被保険者本人にのみ受給権があり、その一方には受給権がありません。
そのため、老齢厚生年金が年金分割の対象となります。
2.年金分割で分割されるもの
年金分割で分割されるのは、婚姻期間中の厚生年金保険の納付実績です。
将来(あるいは現在)支給される年金額が、分割されるわけではありません。
3.年金分割できる場合
年金分割は、婚姻期間中に、夫婦の一方又は双方が、厚生年金に加入していた場合に、手続きすることができます。
4.年金分割の方法
4-1.3号分割
年金分割の典型的な例は、専業主婦であった場合、すなわち、夫婦の一方が厚生年金の被保険者であり、他方がその被扶養者(第3号被保険者)である場合に、第3号被保険者から、被保険者本人に対して、年金分割請求がされる場合です。
このように、第3号被保険者が行う年金分割を、3号分割といいます。
3号分割は、按分割合の合意や裁判を必要とせず、按分割合を2分の1とすることが認められます。
ただし、分割の対象となるのは、平成20年4月1日以降の納付実績に限られます。
なお、3号分割という名前から、1号分割、2号分割があるかのように思えますが、1号分割、2号分割はありません。
詳しい方法はよくあるご質問「年金分割の流れ・方法(3号分割)」をご覧ください。
4-2.合意分割
合意分割は、年金分割の按分割合を、夫婦の合意(合意が調わない場合は調停や審判)で定める年金分割の方法です。
合意分割であれば、夫婦共働きの場合や、平成20年4月1日より前に厚生年金の納付実績がある場合についても、年金分割をすることができます。
詳しい方法はよくあるご質問「年金分割の流れ・方法(合意分割)」をご覧ください。
5.年金分割の期限
年金分割のための情報提供請求や年金分割請求は、原則として、離婚した日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
ただし、以下のケースでは請求期限が変更されます。
1.以下に該当した場合、その日の翌日から起算して6カ月まで、分割請求することができます。
- 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に審判が確定した。
- 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に調停が成立した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
- 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の6カ月以内に按分割合を定めた和解が成立した。
2.分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1カ月以内に限り分割請求が認められます。(年金分割の割合を明らかにすることができる書類の提出が必要です。)
6.共済年金制度について
厚生年金保険制度と共済年金制度に別れていた被用者保険は、平成27年10月から厚生年金保険制度に統一されたため、旧共済年金制度の被保険者も、厚生年金保険制度が適用されることになりました。
関連記事
・よくあるご質問「年金分割のための情報通知書の取得方法は?」
・離婚の用語集「年金分割のための情報通知書【ねんきんぶんかつのためのじょうほうつうちしょ】」