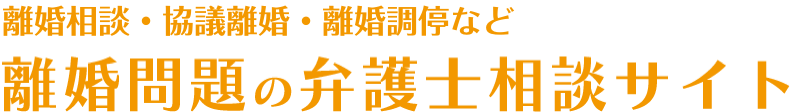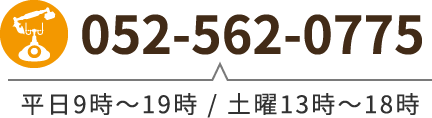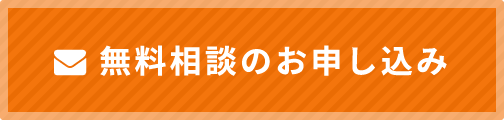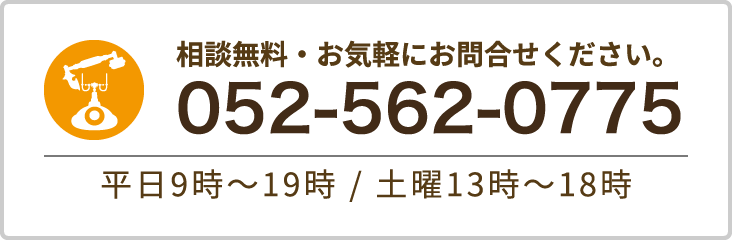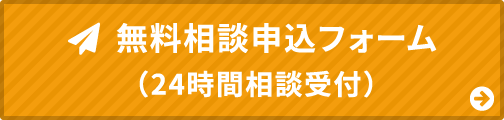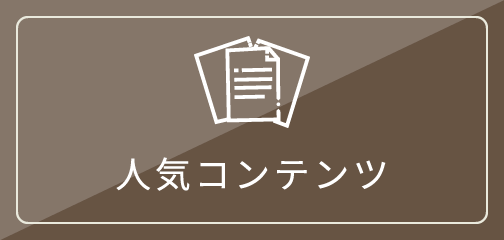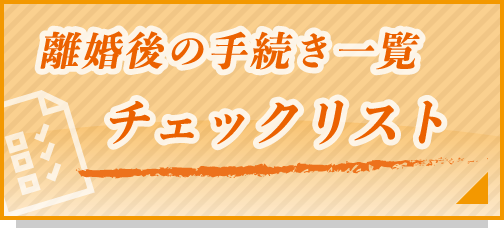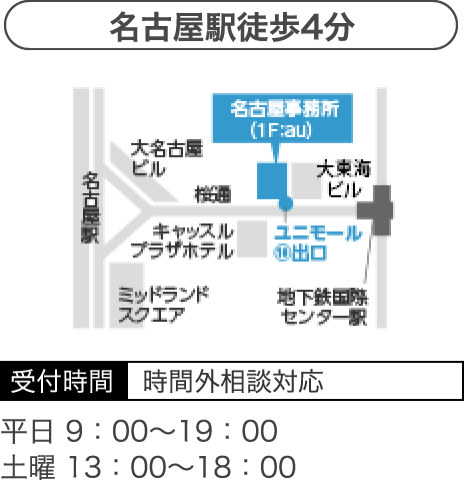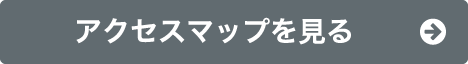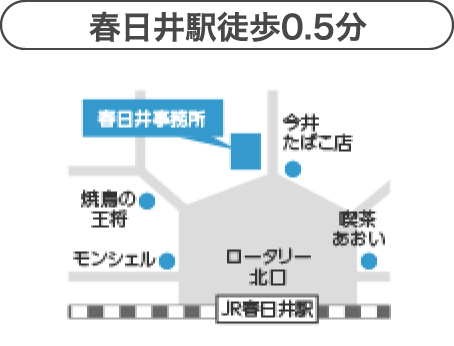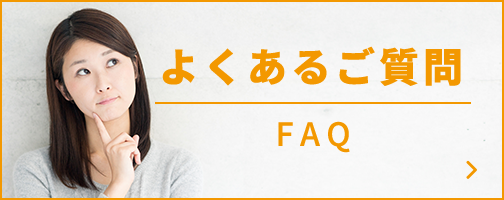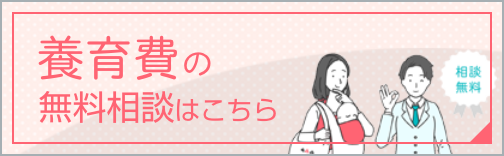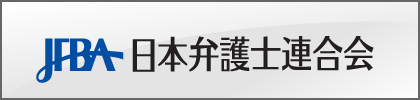民法772条の嫡出推定制度により、離婚後300日以内に生まれた子供は婚姻中に懐胎した元夫の子と推定されるからです。
しかし、離婚後300日以内に生まれた子供であっても、元夫との父子関係を否定できる場合があります。
1.嫡出推定と離婚後300日問題
民法772条により、離婚後300日以内に生まれた子は、妻が婚姻中に懐胎したものと推定されます。
この制度を嫡出推定制度といいます。嫡出推定の適用があると次のような効果が生じます。
- 夫との父子関係が自動的に発生するが、夫は嫡出否認で覆すことができる。
- 嫡出否認ができるのは夫
- 嫡出否認ができるのは子の出生を知った時から1年間
この仕組みにより、子供の父親を早期に確定し、身分関係の安定につなげる制度となっています。
婚姻成立直後や婚姻解消直後に生まれた子供についても、婚姻中に懐胎している限り、嫡出推定による保護を及ぼそうというのが民法の考え方です。妊娠期間は最長でも300日を上回らないことがほとんどであるため、離婚後300日で区切り、同日までに生まれた子供に嫡出推定が及ぶこととして、婚姻中に懐胎した子が嫡出推定の保護から漏れないようにしています。
夫の子供を妊娠中に離婚するケースを想定すれば、そのような扱いは合理的です。元夫は離婚後に生まれる子供に対しても養育費支払いなどの親としての責任を果たすべきですし、その前提となる父子関係を自動的に確定させる方が望ましいからです。
ところが、夫の子ではない場合、不都合が生じます。その場合には夫が嫡出否認をすればよい、というのが嫡出推定の仕組みですが、夫と離婚した場合にはその流れが簡単ではないことがあります。考えられる悩みを列挙してみましょう。
- 元夫と連絡が取れなくなっている
- 元夫からのDVのおそれがある
- 元夫に子供が生まれたことを知られたくない
- 元夫を父親として出生届を出したくない
- 元夫の戸籍に子供が記載されるのを避けたい
これらが理由で、出生届を出さない選択をされる方もいらっしゃいます。そうすると子供は無戸籍になってしまい、さまざまな行政サービスが行き届かないなど、不利益が生じることになります。
離婚後300日以内に子供が生まれた場合に生じるこれらの悩みやトラブルを、「離婚後300日問題」と呼んでいます。
2.離婚後300日問題への対処
上記の悩みをすべて解消できる解決法は、残念ながらありません。この点で嫡出推定制度には問題があり、法制度の大幅な見直しも検討されているところです。
しかし、現状でも以下の方法により一定の対処は可能です。
|
妊娠した時期が離婚後であり、そのことについて医師の証明書がある場合 |
戸籍窓口に医師の証明書を提出することで、元夫を父としない出生届の提出が可能。最も簡単な対処法といえます。 |
|---|---|
|
妊娠した時期に外形的に見て婚姻の実態が失われていた場合 |
裁判所で親子関係不存在確認または強制認知の手続きを行うことにより親子関係を否定し、その結果を戸籍窓口に提出することで、元夫を父としない出生届の提出や戸籍の訂正が可能。DNA鑑定が必要となることが多い。 |
|
元夫から嫡出否認の協力が得られる場合 |
元夫が子の出生を知ってから1年以内に裁判所で嫡出否認の手続きを行うことにより、親子関係を否定し、その結果を戸籍窓口に提出することで、元夫を父としない出生届の提出や戸籍の訂正が可能。DNA鑑定が必要となることが多い。 |
|
上記のいずれにもあてはまらない場合および上記の手続中 |
元夫の子として出生届を提出するか、出生届を提出せず無戸籍状態にするかのどちらかしかない(ただし無戸籍はお勧めできません)。なお、無戸籍であっても住民登録はできる制度があります。 |
※なお、2022年2月14日に法制審議会が「民法(親子法制)等の改正に関する要綱」を発表しており、以上の内容に関しては今後の法改正が予想されます。