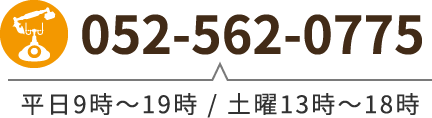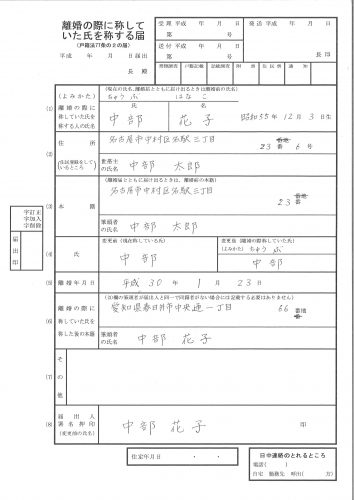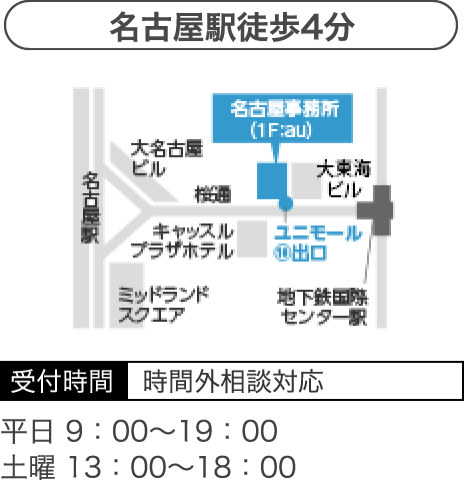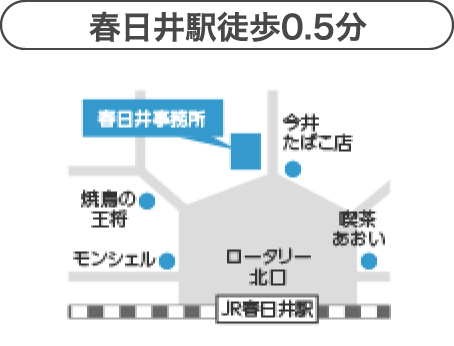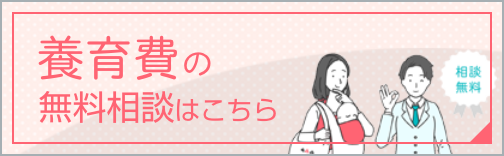離婚について話し合いや調停をしながら、婚姻費用の請求をしなければならない場合は多くあります。しばしば、別居に至っているけれど婚姻費用をまったく払ってもらっていないか、十分に払ってもらっていない状態で、過去の分も請求したいというケースが見受けられます。
しかし、そもそも婚姻費用は過去の分も請求できるのでしょうか。できるとして、いつの分から請求できるのでしょうか。裁判例を中心に解説します。

目次
1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦とその間の未成熟の子からなる婚姻家族が、通常の社会生活を維持するために必要な費用のことです。ここでいう通常の社会生活とは、その家族の資産・収入・社会的地位に照らして相応なレベルのものをいいます。このような婚姻費用について、夫婦は互いに分担するべき義務を負っています(民法760条)。
2.婚姻費用の請求手続
婚姻費用の分担義務が問題となるのは、夫婦の関係にヒビが入った後です。典型的には別居に至った夫婦の間で、収入の少ない方が多い方に対し、生活費の足りない部分を支払ってくれと求める形になります。
当事者どうしが話し合って合意できればそれでよいですが、話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所での手続が必要です。婚姻費用分担は家事事件手続法別表第2が定める審判事項なので、家事審判の対象となります。調停を申し立てることもでき、審判を申し立てても職権で調停に付される場合もあります。調停または審判によって婚姻費用分担額が決定すれば、その金額は具体的な請求権として発生し、以後強制執行等ができるようになります。
3.婚姻費用の分担額の決め方
婚姻費用の分担額は、基本的には夫婦双方の収入と、監護が必要な未成熟子の数により決まります。現在は平成15年に裁判官らの研究会が提案した標準的算定方式が広く採用されており、いわゆる算定表を用いた簡便な算定方法によるのが一般的です。ただし、別居の主な原因を作った側からの請求か否かや、住宅ローンはあるか、大きな学費の負担はあるかなど、修正の要素はあります。
算定表について詳しくは、コラム「婚姻費用の計算に使われる『算定表』って何?」をご参照ください。
4.婚姻費用の始期と終期
さて、このような婚姻費用をいつの分から請求できるのでしょうか。これが婚姻費用の始期の問題です。
反対に、いつの分まで請求できるのかという終期の問題もありますが、終期の方は①婚姻が解消(離婚または死亡により)するまで、または②別居が解消(つまり同居状態の回復)するまでと、はっきりしています。
始期が問題となるのは、別居を始めるなどして扶助が必要になってから、実際に手続きを申し立てるまでに間が空くことが珍しくないためです。何年も経ってから申立てた場合でも常に過去の分を全部請求できるとすると、申し立てられた側の負担が大きくなりすぎるおそれがあります。この問題に対して、一つの答えを示すのが次の判例です。
5.判例(東京高等裁判所昭和60年12月26日決定)
5-1.概要
本事案は、別居中の妻から夫に対して申し立てた婚姻費用分担請求です。未成熟子が2人いて、家庭裁判所の審判では婚姻費用分担額は月15万円と算定されました。妻はこの金額自体も少なすぎるとしつつ、審判で認められた婚姻費用の始期が調停申立時とされたことも不服とし、その4年9ヶ月前の別居開始時からの分を請求できるはずだと主張して、高等裁判所に抗告しました。
5-2.判決の引用
原審判は、相手方の本件婚姻費用分担義務の始期について、抗告人が確定的に請求の意思を表明するに至つた本件調停申立受理の月である昭和五九年九月と解し、同月分からの分担義務を課しているところ、抗告人は抗告理由(2)において、相手方が家を出て別居状態となつた昭和五四年一二月を分担義務の始期とすべきであると主張する。しかしながら、婚姻費用分担義務の始期は、同義務の生活保持義務としての性質と両当事者間の公平の観点から考えれば、権利者が義務者にその請求をした時点と解すべきである。したがつて、昭和五九年九月分からの分担義務を課した原審判は相当であつて、右主張を採用することはできない。
5-3.解説
始期の問題は条文に書いてあるわけではないため、婚姻費用分担義務の性質と公平の観点を踏まえて判断されています。
婚姻費用分担義務の性質に関しては、本決定が述べている「生活保持義務」という概念が重要です。
民法は親族間で経済的に助け合うべき「扶養」の義務を定めていますが、その扶養の程度は関係の近さによって2段階あると解されています。一つは「生活扶助義務」と呼ばれ、自分の方の相応レベルの生活を維持した上で余裕があれば、相手の最低レベルの生活ができるように助けてあげるべき義務という意味です。もう一つが「生活保持義務」であり、自分の生活と同レベルの生活を相手にも維持してやる義務です。夫婦の間と未成熟子に対する親の扶養義務は生活保持義務であり、それ以外の親族に対しては生活扶助義務であるとされています。
過去の扶養料を請求できるかという問題について、そもそもこれを否定する見解もありますが、これは生活扶助義務を念頭に置けば理解できると思います。現在までなんとか生活できた以上、最低レベルの生活はできたのだから、過去の扶養料請求は認める必要がないと考えることもできるからです。これに対して、生活保持義務の場合、なんとか生活できたとしても自分より苦しい生活をさせてきたなら義務を果たしたとはいえません。婚姻費用について過去の分が請求できるということについては最高裁の判例があります(最高裁昭和40年6月30日決定)。本決定が「生活保持義務」の概念を持ち出しているのは、婚姻費用の性質に照らし、過去の分もできるだけ認めてやるべきだという価値判断を示しているといえます。
他方で、別居などにより扶助が必要な状態になっても権利者がそれを放置する(自力でなんとかしようとする)ことはありえます。内心、請求の意思を放棄していることもあるでしょう。そのような場合にまで、何年も経ってからやっぱり請求しようとした場合に全期間分が認められるのだとすると、義務者の負担は大きすぎるように思えます。放棄していたわけでなくても、時間が経過すれば未払い分が蓄積してかなりの金額になります。過去の分を請求できるということはそれをまとめて一時金の形で支払いが命じられるということですから、やはり義務者にとっては酷なことが多いでしょう。これが本決定のいう「公平の観点」の意味だと思われます。
本決定は、妻が「確定的に請求の意思を表明」した時点である調停申立時からの分担義務を課した原審判の判断を支持しているので、請求時を始期とする立場に立っています。一方で、生活保持義務であることをさらに強調すれば、分担が必要だったと認められる限り遡って認めるべきだという考え方もできます。後者の立場に立つ判例も見られますが、現在の主流は請求時説であるようです。
請求時を始期とする立場では、本件のように調停や審判を申し立てた時点が請求時と認定されるほか、それに先立って内容証明郵便で婚姻費用分担の請求をしていたり、夫婦間で婚姻費用分担の合意書を作成していたりして、確定的な請求の意思が証拠上認められればその時点が請求時となります。
6.まとめ
以上から、婚姻費用は請求時以降の分が認められる可能性が高いということができます。
請求する側にとっては、請求時を早い時点に認定してもらえるよう、内容証明郵便で請求しておくなどの対策を早い段階で講じておくことが有用といえます。さらに、別居開始時からの分担を認めても相手方に酷でないような事情(別居期間から請求時まで間もない、相手方が十分裕福であるなど)を主張することで、より早い始期が認められる可能性もゼロではありません。
関連する法律・条文引用
民法760条、家事事件手続法39条、257条