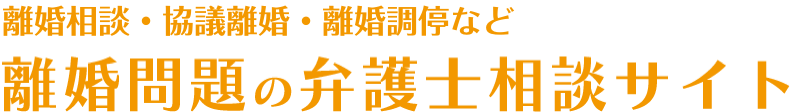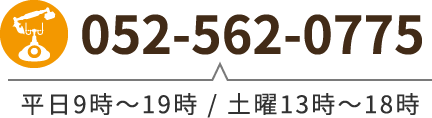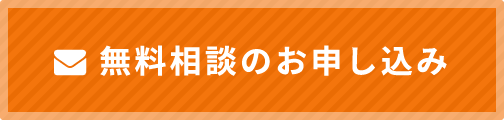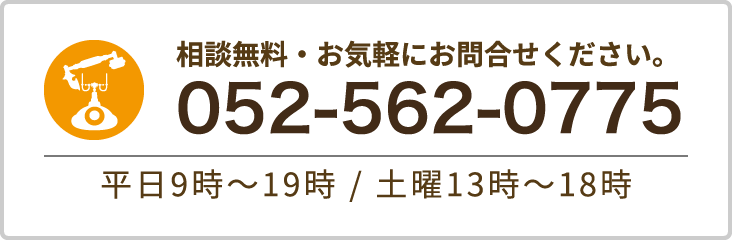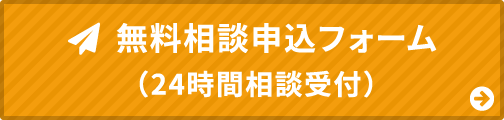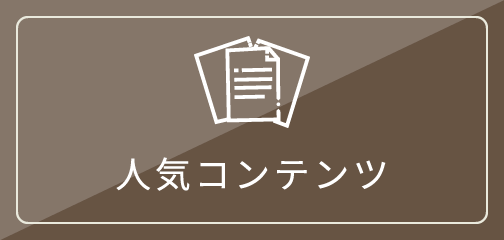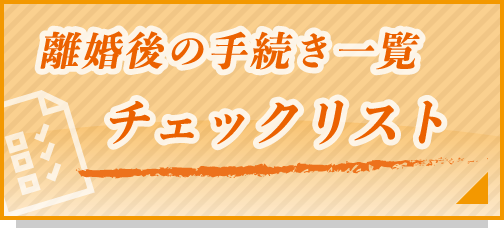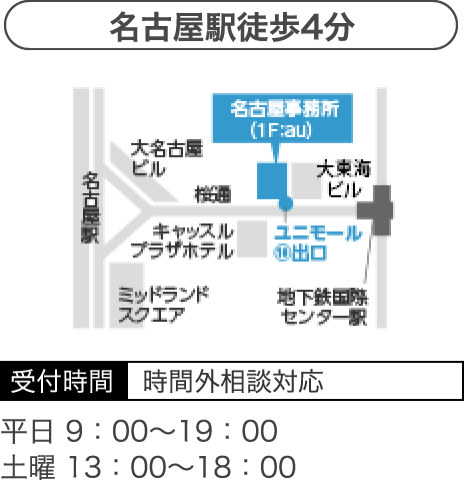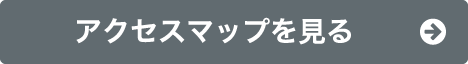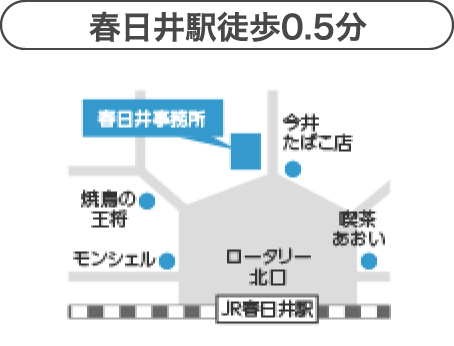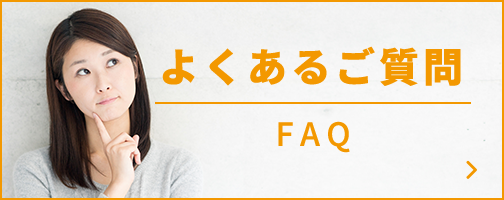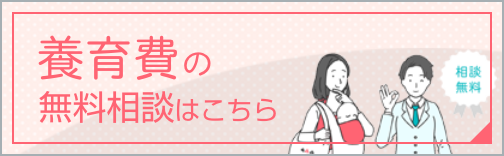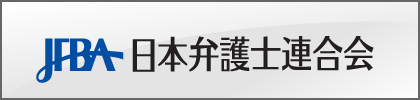家庭裁判所の審判では、目安として10歳前後以上の年齢の子どもであれば、どちらの親と暮らしたいかという子どもの意思が尊重される傾向にあります。年齢が高いほど、子どもの意思に沿った判断になりやすいといえます。
1.親権者指定の判断基準
離婚する際、夫婦の話し合いで親権者を定めることが難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立て(離婚調停の中に含むことも可)、調停もまとまらなければ家庭裁判所が審判で判断することになります。
その際、裁判所は一切の事情を考慮して子の福祉のためにいずれが望ましいかという観点から判断をします。その観点においては次のようにいくつかの重要な要素があり、子どもの意思もその一つです。
- ①監護の継続性維持の原則
- ②乳幼児期における母性優先の原則
- ③子の意思尊重の原則
- ④兄弟姉妹不分離の原則
2.子どもの意思の確認と尊重
親権者指定の家事審判において子どもの意思を考慮すべきことは、法律にも規定があります。
家事事件手続法65条 家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。
同法169条2項 家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第68条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(15歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
実際には15歳未満の子どもに対しても、年齢等に応じ適切な方法で意思を把握した上で判断する運用となっています。
3.子供の意思が判断に影響する程度
子供の意思が尊重されるといっても絶対ではなく、両親それぞれの監護能力、経済力、健康状態などさまざまな事情が考慮される中で、比較的重要な一要素として働くものです。
たとえば、親権者変更の事例で、現在親権者である母親の監護能力に問題があり、三人きょうだいの上二人は父親との生活を希望しているが、12歳の次男だけは母親との生活を希望していたという事情のもと、上二人のみについて親権者変更を認めた事例があります。
このケースでは、母親の監護能力やきょうだい不分離の原則よりも優先して、12歳の子供の意思が尊重されたといえます。
なお、子供の意思が形成される過程で、現在一緒に暮らしている者からの不当な誘導や洗脳のような状況があるケースも考えなければなりません。そのような状況が認められる場合には、子供の意思が尊重される度合いは後退します。