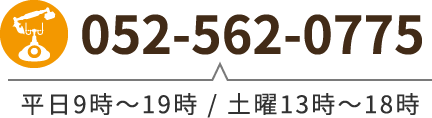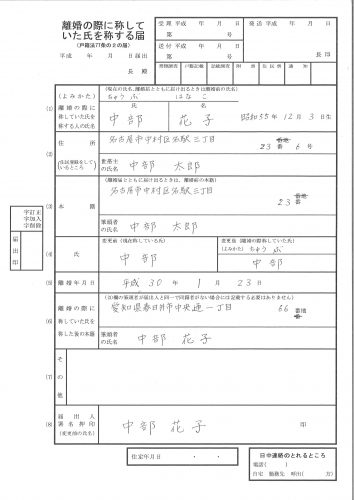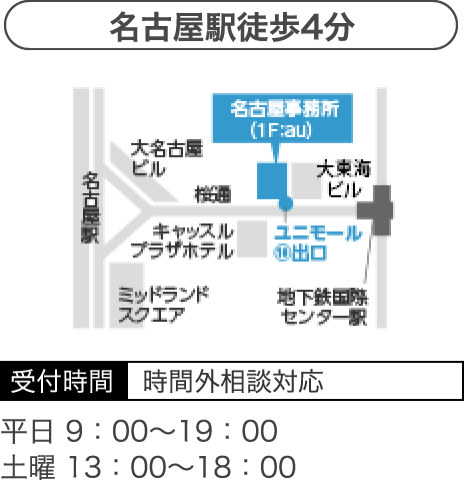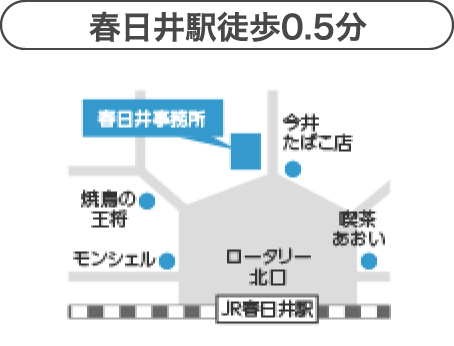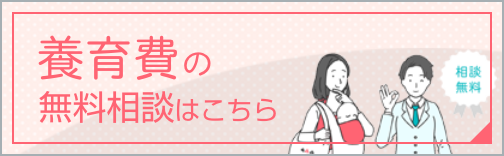裁判で離婚を求める際の大きな理由の一つに「婚姻関係の破綻」がありますが、長年にわたって別居しているなどにより破綻が認められるとしても、その破綻の原因が過去の自分の浮気にあるような場合、離婚請求は許されないのかという問題があります。有名な最高裁判例を中心に解説します。

1.離婚原因と離婚請求
まず離婚の基本的な仕組みですが、離婚は協議離婚や調停離婚など、双方の合意に基づいて成立するものと、片方が同意しなくても裁判で成立させることのできる裁判離婚とに大きく分けられます。裁判離婚では、民法770条1項が定める5つの離婚原因の有無を判断します。
具体的には①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つであり、このいずれかがあると認定されれば、離婚が認められます。
2.有責配偶者とは
これら離婚原因のうち、①〜④は具体的な事情ですが、⑤は抽象的で、さまざまな事情から判断して客観的に婚姻関係が破綻しているといえるかどうかにより決まります。
客観的に破綻といえればよいということになると、その原因がどちらにあるかとは無関係に判断することができそうですが、果たしてそれでよいのでしょうか。
破綻の原因を作った側の配偶者のことを有責配偶者とよびますが、有責配偶者から破綻を主張して離婚を請求することは許されないのではないかという問題があるのです。
3.対立する2つの考え方
上記⑤の離婚原因が存在していること自体が、「破綻主義」とよばれる考え方を示しています。どちらが悪いということではなく、破綻していればもはや離婚を認めてよいではないかという考え方です。
この考え方を推し進めれば、有責配偶者であっても離婚請求は許されるという立場になります(積極的破綻主義)。
一方、破綻主義の下でも正義や倫理に照らして一定の制約はあるはずだとして、有責配偶者の離婚請求は許されないと考える立場もあります(消極的破綻主義)。
4.踏んだり蹴ったり判決
かつての判例は、はっきりと消極的破綻主義の立場を取っていました。
愛人を作って出て行った夫が、別居2年で破綻等を主張して離婚を請求した事案で、最高裁は離婚を認めず、有責配偶者からの離婚請求は許されないというルールを示しました(最高裁昭和27年2月19日判決)。
判決文の中で、愛人を作られた上に離婚まで認めては妻にとって踏んだり蹴ったりだという趣旨を述べたので、俗に「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれています。
しかし、この判例は以下に説明する最高裁昭和62年9月2日判決により、大きく変更されることになります。
5.最高裁昭和62年9月2日判決
5-1.事案の概要
本事案の夫婦は、昭和12年に婚姻しましたが、子供が生まれず昭和23年に養子をとりました。ところが昭和24年、夫が養子の実親である女性と関係を持っていたことが発覚します。これがきっかけで夫婦は不和となり、同年頃から別居して夫はその女性と同棲を始めます。
その後夫と女性の間にさらに子供も生まれています。昭和26年頃、夫から離婚の訴えを提起していますが、その際には有責配偶者からの離婚請求であることを理由に棄却されました。
しかしその後も別居は続き、昭和59年、別居期間が35年に及んだところで夫から再び離婚を求めて調停を申し立てました。妻は離婚に応じず、離婚の訴えが提起されたものです。
5-2.判旨の引用
有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできないものと解するのが相当である。
5-3.解説
本判決は、従来の踏んだり蹴ったり判決の「有責配偶者からの離婚請求は絶対に許されない」という立場を変更し、「有責配偶者からの離婚請求であっても許される場合がある」という立場をとったものです。
まず、判決は婚姻共同生活の実体が欠けており、その回復の見込みもない場合に戸籍上の婚姻をいつまでも残しておくことは不自然だと述べ、破綻主義の考え方を強調しています。
それと同時に、離婚をどのように認めるかは社会的な秩序に関わることであるから、やはり正義や倫理の価値観とも調和していなければならないとし、離婚請求にも信義則による制約があるのだという趣旨を述べています。
ここから分かるとおり、破綻主義に一定の制約を加える必要があるという考え方そのものは踏んだり蹴ったり判決と変わりません。しかし、その中でさらに踏み込み、具体的な判断基準を示しつつ、許される場合か許されない場合かを個別に判断すべきだとしたのです。
判決が挙げる具体的基準を説明します。
まず判断要素として以下のものが挙げられています。
- 有責配偶者の責任の態様・程度
- 相手方配偶者の婚姻継続についての意思・請求者に対する感情
- 離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態
- 夫婦間の子(とくに未成熟子)の監護・教育・福祉の状況
- 別居後に形成された生活関係(内縁関係が形成されている場合にはその相手方や子らの状況)
- 時の経過が上記諸事情に与える影響
その上で、本件に即して次のようにルール化した判断基準を示しました
[1]別居期間が年齢や同居期間と対比して相当の長期間といえること
[2]夫婦間に未成熟子(親から独立して生計を営むことができない子)がいないこと
[3]離婚により相手方配偶者が苛酷な状況に陥るなど、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと
以上の条件がある場合には離婚を認めてもよい。
本判決以降はこのルールを踏まえた判例が展開していますが、若干の注意点があります。
まず、[1]の別居期間については、どの程度長ければ相当の長期間と認められるのか、まだ明確なルールはありません。
10年で認めた判例(最高裁昭和63年12月8日判決)と、8年で認めなかった判例(最高裁平成元年3月28日)があります。一方で、7年半で認めた判例(最高裁平成2年11月8日判決)も出ています。
そもそも[1]の条件は絶対的なものではなく、いろいろな事情を総合して信義則上許されるかどうかを判断する中の一つの要素であり、他の事情との兼ね合いで短めでも認められることもあれば、長めでも認められないこともあるのだといえます。
[2]の未成熟子の存在についても、別居期間14年で未成熟子がいる事案で離婚を認めた判例(最高裁平成6年2月8日判決)が出ています。
これも同様に、他の事情との兼ね合いということができますが、[1]と比べれば厳しい判断がなされているようです。とくに、重い障害があるお子さんがいる事案では、成人していても未成熟子と同様に扱い、離婚を認めない判例が見受けられます。
6.まとめ
現在の判例ルールの下では、有責配偶者であっても離婚が認められる可能性があるという結論になります。離婚が認められるためには、別居期間が相当長期間であることと、未成熟子がいないことが基本的な条件ではありますが、それだけではなくさまざまな事情を主張する必要があります。
たとえば、相手方には十分な収入があって離婚後の生活に不安はないとか、財産分与や養育費をしっかり支払う準備があるとか、相手方としても愛情はまったくないのに報復感情で離婚を拒絶しているだけであるとかの事情が考えられます。離婚を請求される側の立場からは、これらの逆の事情を主張して争うことになるでしょう。主張の整理と証拠の準備が重要となりますので、弁護士によくご相談ください。